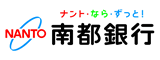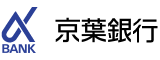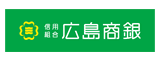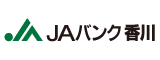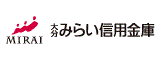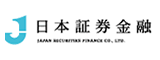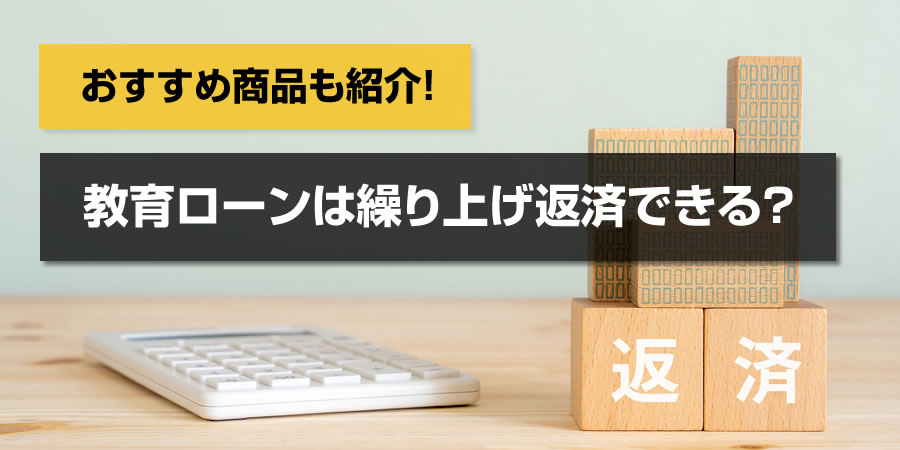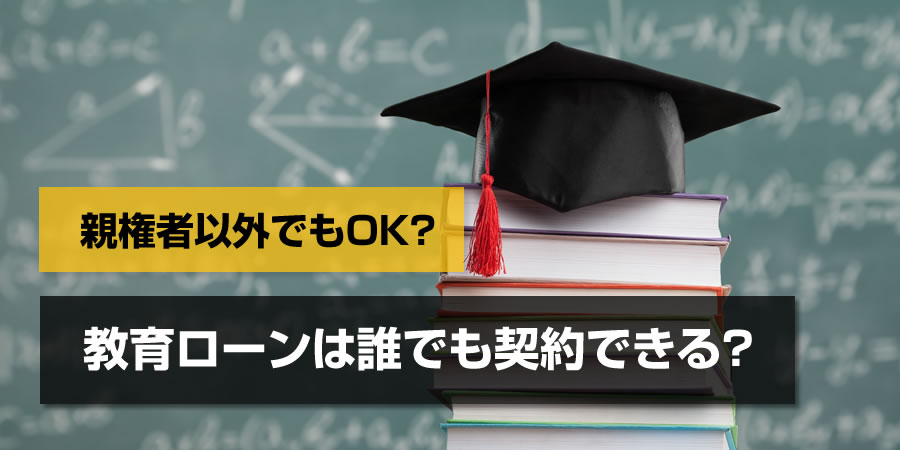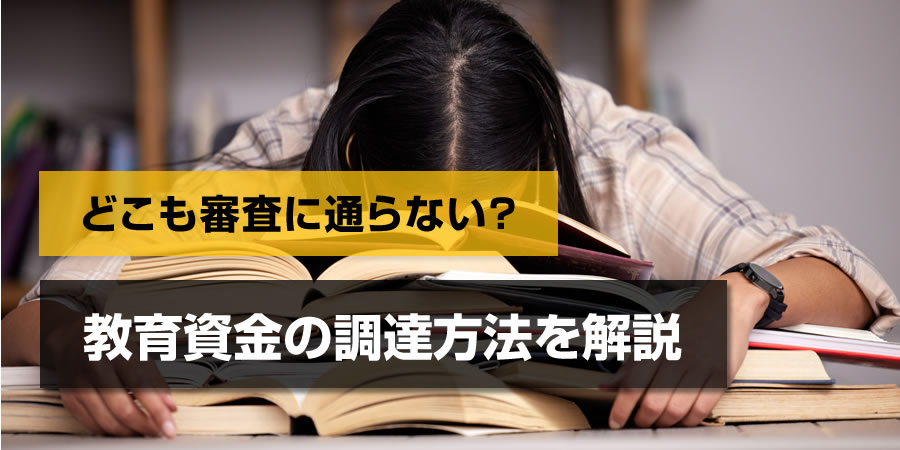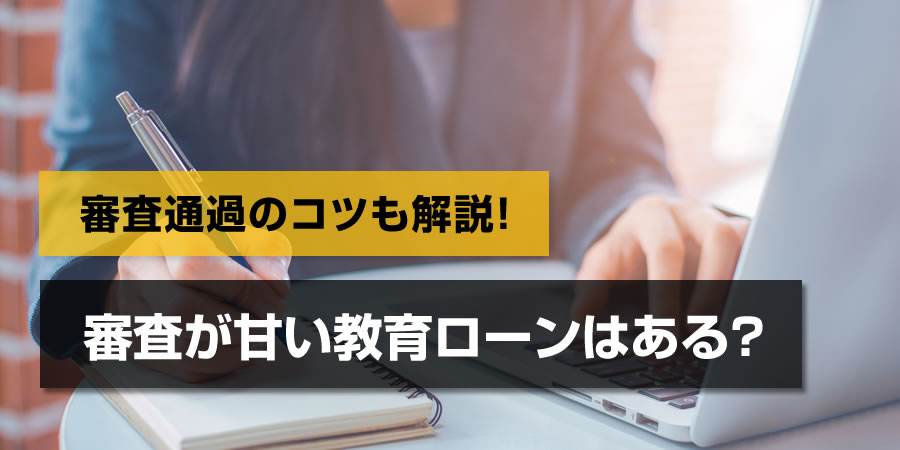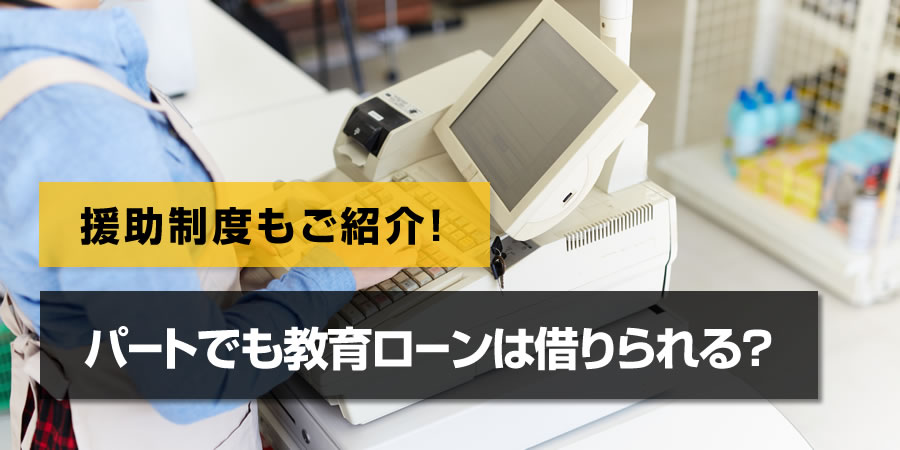【第24回】医学部の学費はどれくらい?教育ローンの種類・比較と注意点を徹底解説
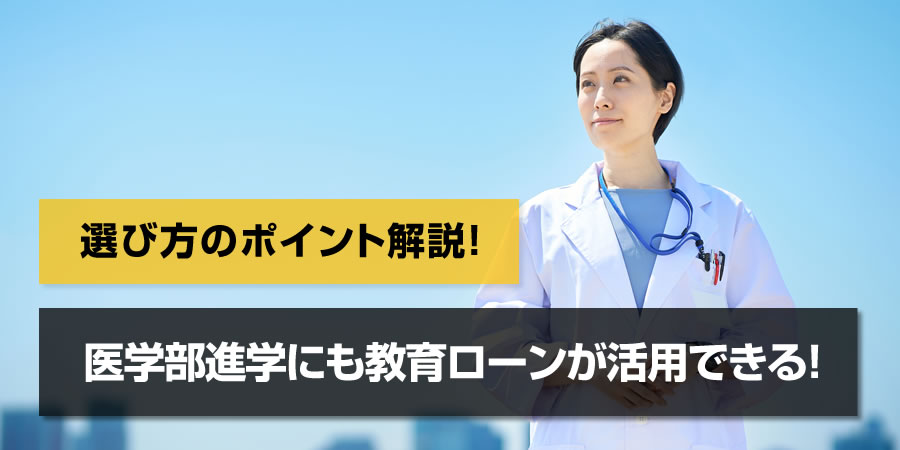
この記事は約12分30秒で読むことができます。
お急ぎの方、教育ローンのランキングを知りたい方は、このページ下部のこちらをご覧ください。
1 医学部の入学金・学費はいくらかかるの?相場を確認

医学部の学費は進学先が国立か、公立、もしくは私立によって大きく異なります。国立大学の医学部の標準額は、入学金が28万2,000円で授業料は1年で53万5,800円です。医学部は基本的に6年制なので、卒業までに大学へ支払う金額は349万6,800円になります。
公立大学を選ぶ場合、出身地によって入学金が異なる点に注意しましょう。結果として、地域出身者なら、国立大学と同じ水準ですが、ほかの地域の出身者だと高めになる傾向があります。
また、2020年度から千葉大学と東京医科歯科大学の入学者に関しては、1年の授業料が64万2,960円、6年間で413万9,760円に変更されているので注意しましょう。
| 入学金 | 28万2,000円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 53万5,800円 |
| 総額(入学金+年間授業料×6年間) | 349万6,800円 |
| 入学金 | 39万1,305円 |
|---|---|
| 年間授業料 | 53万6,363円 |
| 総額(入学金+年間授業料×6年間) | 360万9,483円 |
(参考)文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」[pdf]
私立大学の場合は、大学ごとに学費を決めているので子どもがどこに入学を希望するかで家計の負担が大きく変わります。
日本私立医科歯科大学協会によると、6年間にかかる教育費は約3,200万円です。
今回紹介したのは大学に支払うお金だけですが、子どもを大学に通わせると交通費や交際費などもかかります。大学が家から遠い場合は、寮に入ったり、下宿したりする費用も必要です。
ちなみに、第60回学生生活実態調査の結果によると、下宿生の住居費は毎月約5万6,000円、親からの仕送りは毎月約7万2,000円となっています。
子どもを大学に通わせるためには、学費以外の費用もかかることを念頭においておきましょう。
2 教育ローンとは?仕組みと審査の基本

教育ローンとは、教育に関する費用に充てるためのローンです。
資金使途が「教育に関する費用」に限定されており、ほかの目的での利用は禁止されています。
教育に関する費用の内容は、教育ローンを提供する金融機関によって異なり、幅広い使途に利用できる金融機関もあれば、学校に納付する金額のみを対象としているところもあります。
教育ローンは「国の教育ローン」と銀行などの金融機関が提供する「民間の教育ローン」の2つに分けられるので、下記でそれぞれの特徴を確認していきましょう。
2-1 国の教育ローン
国の教育ローンとは、日本政策金融公庫の教育一般貸付を指します。教育一般貸付は返済期間が15年と長めに設定されていて、完済するまでに金利が変わらない固定金利が適用されます。金利の種類については後ほど詳しく解説するので、合わせてチェックしてください。
借入可能額は、民間の教育ローンと比較して少なめの350万円です。
ただし、世帯条件や子どもの数によっては450万円まで拡大されます。
教育ローンをはじめとした借り入れをするためには、審査に通る必要があります。国の教育ローンには所得制限が設けられており、世帯年収の上限を超える場合は利用できない点に注意しておきましょう。
2-2 銀行など民間の教育ローン
民間の金融機関で教育ローンを取り扱っているところとしては、銀行や信用金庫、労働金庫などがあります。
民間の場合は、金融機関や商品によって教育ローンに違いがあります。そのため、申込みの前に利用条件や借入内容をよく比較・検討することが大切です。
返済期限は金融機関によって幅があり、5年~18年程度に設定されています。借入金額や返済期間によっては毎月の返済額が家計に負担をかける可能性があるため、無理のない借入金額や返済期間を意識しましょう。借入可能額は1,000万円程度の金融機関が多いので、国の教育ローンよりも学費などが高額でも安心できます。
また、民間の金融機関では医学部や歯学部を対象に借入可能額を3,000万円、返済期間を20年としている教育ローンもあるので必要に応じて検討してみてください。
3 教育ローンとフリーローン・奨学金との違いを解説
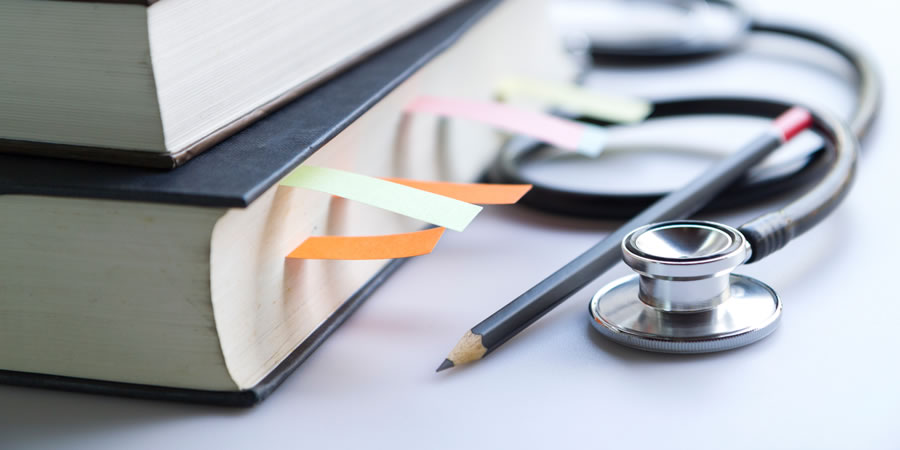
教育に関する費用を調達する手段として、教育ローン以外にも「フリーローン」や「奨学金」の利用も考えられます。
ここでは教育ローンとフリーローン、そして奨学金の違いについて解説します。
3-1 教育ローンとフリーローンの違い
医学部進学に利用できるローンは、大きく教育ローンとフリーローンの2つに分けられます。
教育ローンとは、資金使途が教育関連のものに限定されている目的別ローンの1つです。借りたお金を自由に使えないかわりに、金利が低めに設定されています。
一方、フリーローンは資金使途が限定されておらず、原則自由に利用できますが、教育費を借り入れる目的で利用する場合は教育ローンに比べると金利が高くなるため向いていません。
そのため、保護者が子どもの学費のためにお金を借りる場合は、教育ローンを利用するのが一般的です。フリーローンは習い事の用具など、教育ローンの資金使途対象外となる教育関連資金に利用しましょう。
3-2 教育ローンと奨学金の違い
教育ローンを借りる前に検討する方が多いのは、奨学金ではないでしょうか。奨学金とは、子ども本人が契約者となってお金を借りる仕組みです。加えて、連帯保証人や機関保証が必要になる場合があります。そのため、奨学金の返済責任は保護者ではなく、契約者である学生本人が負います。
また、教育ローンと奨学金は返済を開始するタイミングにも違いがあります。教育ローンは約定返済日から支払いが始まりますが、奨学金は貸与期間が終わってからお金を返済する仕組みです。ただし、教育ローンにも在学中は元本の返済を据え置く「据置制度」が用意されています。
現状の家計で子どもの学費をまかなうのが難しい場合は、奨学金で支払いを先送りにするのも選択肢の一つです。借入可能額は教育ローンが一括で1,000万円ほど、奨学金は第二種奨学金の場合、私立大学の医・歯学の課程を対象とする貸与月額は2万円~16万円(1万円刻み)です。教育ローンは一括借入型とカードローン型がありますが、奨学金は毎月定額が振り込まれます。
4 教育ローンの使い道は学費だけではない!

「教育ローンは学費にしか使えない」と考えている方も多いですが、授業料や入学金以外の費用にも充てられます。例えば、下宿での生活にかかる費用や引越し代金に使えます。
そのほか、以下の費用にも一般的に利用可能です。
- 受験料
- 入試会場までの交通費
- 教科書代
- 通学費
- 国家試験対策費用
- 実習にかかる費用
医学部を目指すための塾や予備校などへの通学費も借りられることがあるので、教育ローンの資金使途は幅広いといえるでしょう。
国の教育ローンは比較的幅広い資金使途に対応していますが、民間の教育ローンは提供する金融機関によって資金使途が異なるので、申込む前に希望の資金使途に対応しているか確認するようにしましょう。
4-1 教育ローンの利用がおすすめの方

ここまで解説したとおり教育ローンは、国の教育ローンや奨学金とは審査基準が異なります。教育ローンの利用がおすすめなのは、次のような方です。
4-2 教育費用として高額な借り入れが必要な方
教育ローンによっては、医学部などに進学する方に向け、限度額を高額に設定しているものもあります。国の教育ローンやフリーローンよりも高額な借り入れが、低金利で利用できます。
4-3 奨学金の利用条件を満たさず、奨学金を利用できない方
奨学金には所得制限が設けられているほか、合わせて学力基準も満たす必要があります。奨学金を申し込んでも採用されなかった場合には、教育ローンの利用を考えてみましょう。
5 教育ローンの特徴と融資条件を種類別に解説

教育ローンには、国の教育ローンのほか、銀行の教育ローンや労働金庫が提供する教育ローンもあります。 ここでは、それぞれの教育ローンの特徴について解説します。
5-1 国の教育ローンの特徴・利用条件
国の教育ローンとは、日本政策金融公庫が行っている「教育一般貸付」のことです。
固定金利で借りることができ、低所得世帯や1人親世帯などには金利の優遇措置が設けられている点が特徴です。返済期間も20年以内と長く、毎月の返済額を減らせる効果も期待できます。
借入金額の上限は350万円ですが、これは子ども1人あたりの金額です。子どもが2人いれば700万円まで借りられます。また、条件によっては450万円まで上限が拡大されますので、必要なら条件を調べてみましょう。
| 金利 | 年3.15%(固定金利) |
|---|---|
| 借入金額 | 350万円(要件を満たすことで450万円まで増額可能) |
| 借入条件 | ・子どもの数に応じて設定された世帯年収の上限額以下 ・進学先の学校が修業年限3ヶ月以上で、中学卒業以上の方を対象とした教育施設である |
(参考)国の教育ローン|日本政策金融公庫
金利は2025年10月時点の情報です。また、低所得世帯やひとり親家庭などに対しては、0.4%の金利優遇が適用されます。
5-2 銀行の教育ローンの特徴・利用条件
銀行の教育ローンは、メガバンクや地方銀行などが提供しており、借入可能額が高額な傾向にあります。
| 金利 | 金融機関によって異なる(変動金利もしくは固定金利) |
|---|---|
| 借入金額 | 金融機関によって異なる(一般的には500万円~1,000万円だが、医学部などに進学する場合に限り、3,000万円までなど高額な借入金額を設定しているところもある) |
| 借入条件 | 金融機関によって異なる |
銀行の教育ローンは、提供する金融機関によって特徴や利用条件が異なります。利用を考える際には、複数の金融機関を比較して最終的に決めるようにしましょう。
また、銀行の教育ローンでは、在学中は金利のみを支払い、卒業後に元本の返済が始まる元金据置制度を設けているところもあります。在学期間中は教材費や実習費など多くの費用がかかることも予想されるため、在学期間中の返済額を抑えたいと考えるなら、元金据置制度を活用しましょう。
ちなみに元金据置制度は国の教育ローンでも用意されています。
5-3 労働金庫の教育ローンの特徴・利用条件
労働金庫の教育ローンとは、日本各地にある労働金庫が提供する教育ローンで、原則として労働金庫に出資している団体構成員の方に対して提供されますが、団体構成員でなくても利用は可能です。ここでは、中央労働金庫が提供している教育ローンについて紹介します。
なお、データは2025年10月時点のものです。
| 金利 ※団体会員の構成員の方向け |
年2.40%~2.60%(変動金利・証書貸付型) 年3.050%(変動金利・カード型) 固定金利の選択も可能 |
|---|---|
| 借入金額 | 1万円以上2,000万円以内 |
| 借入条件 | 中央労働金庫に出資している団体構成員、もしくは自宅か勤務先が中央労働金庫の営業エリア内にある給与所得者で、以下の条件を全て満たす方 ・申込時の年齢が満18歳以上、最終返済時年齢が満81歳未満 ・同一勤務先に1年以上勤務している ・前年税込年収が150万円以上あり、安定継続した収入がある |
教育ローン[証書貸付型]|中央ろうきん(中央労働金庫)
労働金庫の返済期間は20年以内となっており、元金据置制度も用意されています。ただし、元金返済据置期間は5年以内とされている点に注意しておきましょう。
給与所得者だけではなく、契約社員やパート・アルバイト、自営業者の方も利用できますが、自営業者の方は営業年数が3年以上なければなりません。
6 医学部進学で教育ローンを利用するメリット

ここでは、医学部に進学するにあたって、教育ローンを利用するメリットについて解説します。
主なメリットは、以下の3つです。
- 学費の高い私立医学部でも選択肢にできる
- 医師として安定収入が得られるから返済しやすい
- 奨学金や特待制度の不足分を補える
6-1 学費の高い私立医学部でも選択肢にできる
私立の医学部だと、学費の総額が数千万円にのぼることも珍しくありません。しかし、それだけの自己資金を用意するのが難しい方も多いのではないでしょうか。
教育ローンを利用することで、自己資金がなくても学費を準備することができ、進学を諦めることもなくなります。
6-2 医師として安定収入が得られるから返済しやすい
医学部に進学し、医師国家試験に合格すれば、医師として就職できます。医師の給与はほかの職業よりも比較的高いと言われており、長期的に見ればローンの返済計画を立てやすい点もメリットです。
6-3 奨学金や特待制度の不足分を補える
奨学金を借りられたとしても、お金が振り込まれるのは入学してからです。入学金や受験にかかる費用などは自分で準備しなければなりません。
大学によっては入学時だけで400万円程度かかるケースもあり、奨学金や国の教育ローンでは賄えない可能性もあります。
また、特待制度も基準が厳しくなかなか利用できないケースも考えられます。そのようなときに教育ローンを利用することで、奨学金や特待制度の不足分のみならず、進学費用全体をカバーできます。
7 医学部進学で教育ローンを利用するデメリット

医学部進学において、教育ローンを利用するメリットは前章で述べたとおりですが、利用する際には以下のデメリットがある点もしっかりと理解しておきましょう。
7-1 返済期間が長期化しやすい
医学部にかかる学費の総額は、進学先によっては数千万円にものぼるため、借入額が高額になりやすい点がデメリットです。
中には返済期間が15年以上になるケースもあり、卒業してからも長期的にローンを抱えることになってしまいます。返済額によっては家計に負担がかかる可能性もあります。
7-2 利息負担が大きい
医学部進学のために教育ローンを利用するとなると、借入金額が大きく、返済期間も長く設定するため、最終的な返済総額が高くなります。
近年は国の教育ローンの金利も上昇しており、民間の教育ローンと同水準になりつつあります。「国の教育ローンだから」と安心せず、制度の条件や返済計画をしっかりと比較し、検討するよう心がけましょう。
7-3 卒業後に医師にならなかった場合の返済リスクがある
医学部に進学したからといって、卒業後必ず医師になるとは限りません。医師になるには国家試験に通らなければなりませんし、研修医の時点で医者が向いていないと考え辞めてしまう可能性もあります。
もし、医師以外の職業を選んだ場合、収入が思ったよりも少なくなり、教育ローンの返済が重くのしかかってしまいます。
8 医学部向け教育ローンを比較するポイントは?

子どもが医学部に通う場合に利用できる教育ローンには多くの選択肢がありますが、この章では申込先を選ぶときのポイントを解説します。教育ローンの比較方法がよく分からない方は、必見です。
8-1 借入可能額(いくらまで借りられるか)
医学部は、ほかの学部と比べると学費が高額です。そのため、教育ローンを選ぶときは借入可能額を確認しなければいけません。借入可能額とは、金融機関から借りられる最大金額で、金融機関のWebサイトやパンフレットなどに記載されています。
借入可能額は審査によって決定されますが、場合によっては借入可能額いっぱいまでお金を借りても足りない可能性があることを念頭に置いておきましょう。
国の教育ローンの箇所で説明したとおり、日本政策金融公庫の借入可能額は350万円(ただし、子どもの人数や世帯条件によっては450万円まで可能。また借入額は子ども1人あたりの金額)、民間の金融機関は500万円~1,000万円前後が一般的です。
医学部に特化した特別な教育ローンであれば3,000万円までを上限に借りられる場合もあります。ただし、あくまでも上限であり、実際に借りられる金額は審査によって決定します。
ただし、金融機関からお金を借りると必ず金利を含めて返済しなければいけません。子どもの進学に必要な額を教育ローンでまかなえるかだけでなく、無理なく返済できるかを考えながら、最終的に借り入れる金額を決めるようにしましょう。
8-2 金利(利息負担の大きさ)
金利は借入金額に対する利息の割合で、金利が高いほど家計の負担になります。また、利息は返済残高を基に計算されるため、お金を借りている期間が長くなるほど、発生する金額が大きくなる特徴もあるので覚えておきましょう。
特に、医学部の場合は学費の支払い期間が短くても6年間かかります。そのため、ほかの学部と比べるとわずかな金利の差が返済総額に影響しやすくなるので注意が必要です。
金利には、固定金利と変動金利の2種類があります。固定金利は返済期間中に金利が変わることはありませんが、変動金利は景気の変動を受けて変動する可能性があります。一般的には、変動金利のほうが金利は低いので、利息の負担をできるだけ抑えたい場合は変動金利の教育ローンを検討するといいでしょう。
変動金利を選ぶ場合は、利上げを推し進めている金融政策の動向を見ながら判断することをおすすめします。なぜなら今後の利上げにより、将来の毎月の返済額が増える可能性があるからです。
なお、日本政策金融公庫の国の教育ローンの場合は固定金利3.15%で、変動金利は用意されていません。民間の金融機関であれば変動金利の教育ローンも用意されていますが、実質年利は1%未満~4%台までさまざまです。
8-3 返済方法(据置・返済期間の柔軟性)
教育ローンの借入方法には、一括借入型とカードローン型の2種類があります。一括借入型は、その名のとおり、必要金額全額を借りて毎月一定額を返済する仕組みです。証書貸付型とも呼ばれています。
一方、カードローン型は、申込みのときに限度額を設定して、必要なときに必要な金額をATMで引き出したり返済したりできるのが特徴です。極度型とも呼ばれています。
使い分けとしては、まとまった金額が必要なときは一括借入型が向いています。初年度の納入金を補てんする場合などに利用するといいでしょう。
対して、カードローン型は長期にわたって定期的にお金を用意したいときに適しています。授業料の分納を考えているなら、カードローン型の教育ローンを選択するといいでしょう。
また、在学期間中は利息のみの返済でよく、卒業後に元本を合わせて返済する元金据置制度を設けている金融機関もあります。在学中は学費以外にもさまざまな支出が考えられますので、在学中の返済負担を抑えるなら元金据置制度の利用も有効です。
9 医学部向け教育ローンを利用するときの注意点

医学部に進学する際に利用する教育ローンでは、高額な借り入れを行うケースもあります。医学部の教育ローンを利用する際には、以下の点に注意しておきましょう。
9-1 借入額と返済計画をしっかり立てる
子どもが医学部に進学すると、入学金はもちろん、授業料や教材費がかかります。自宅外通学になると、下宿費用や生活費の仕送りも必要です。
とはいえ、借りられる金額にも限度があるため、シミュレーションなどを利用してしっかりとした返済計画を立て、無理のない範囲で借り入れることが大切です。
借り入れる金額を考える際には、返済負担率(年収に占めるローン全体の年間返済総額)も考えてみましょう。ここでいうローンとは、教育ローンだけでなく、住宅ローンなどほかのローンも含まれます、無理のない返済負担率は25%程度といわれていますので、実際にどのくらいまで借りられるかを考える指標の一つになるでしょう。
9-2 在学中の元本据置制度を確認する
通常なら4年間で終了する他の学部と異なり、医学部は6年間通わなければなりません。その分多くなる費用を借り入れで補おうとすると、毎月の返済額は高額になってしまいます。
そのため、在学期間中は利息のみを支払い、卒業後に元本を合わせて返済する元金据置制度があるかを確認しましょう。在学中の返済の負担が楽になれば、その分ほかの費用にあてられます。
ただし、元金据置制度を利用すると、卒業後の返済額が大きくなってしまいます。
元金据置制度を利用するなら、卒業後の返済がどのくらいになるのかを事前にシミュレーションし、無理のない返済であるかを確認する必要があります。
9-3 金利タイプ(固定・変動)の違いを理解する
金利タイプには、固定金利と変動金利があります。
固定金利は完済するまで返済額が固定しているため、返済計画が立てやすいというメリットがあります。変動金利は原則として半年に1度金利が見直されます。
一般的に固定金利よりも変動金利のほうが金利は低い傾向にありますが、同時に金利上昇リスクもあることを覚えておきましょう。
9-4 保証人・担保の要否を事前に確認する
国の教育ローンは原則として連帯保証人が必要です。連帯保証人が立てられない場合は、保証機関を利用することで連帯保証人を不要にできます。ただ、保証機関を利用する場合は、保証料の支払いが必要です。
民間の教育ローンは保証人を不要としているところが多く、保証会社を利用しているケースが一般的です。
教育ローンを借り入れる際には、保証人の有無や保証会社を利用した際の保証料、また担保の必要性なども確認しておきましょう。
9-5 医師修学支援制度の利用も検討する
自治体によっては医師修学支援制度を設けているところもあります。医師修学支援制度とは、自治体が医学部生に修学資金を貸し、卒業後に一定期間、指定した医療機関で勤務すれば返済が免除される仕組みです。
ただし、条件を満たさなかった場合は、借り入れた金額を全額返済しなければならないため、注意しておきましょう。
教育ローンを利用する前に、住んでいる自治体でこのような支援制度があるのか、また利用するための条件を確認することで、卒業後の返済負担を減らせる可能性があります。
9-6 奨学金や特待制度との併用を検討する
申込条件に当てはまるなら、奨学金や国の教育ローンとの併用も考えましょう。また、大学によっては特待生制度を設けているところもあります。特待生に選ばれると入学の際の費用を抑えられる可能性もありますので、希望する進学先にそのような制度が用意されているかを事前に確認しておくことをおすすめします。
ちなみに奨学金には、返済不要の給付奨学金と返済が必要な貸与奨学金の2種類があります。また、貸与奨学金には第一種奨学金と第二種奨学金に分かれており、第一種奨学金には利息がかかりません。ただ、利息がかからない分、審査基準は第二種奨学金よりも厳しくなっています。
10 教育ローンの検討にはローンプラスなどの比較サイトの活用が便利!

どの教育ローンを利用するか悩んだ時には、比較サイトの利用も有効です。
ローンプラスでは、複数の教育ローンを一度にまとめて商品を比較でき、大変便利です。
また、実質年率や金利体系、借入可能額、審査回答期間などのポイントが記載されているため、自分に合ったローンを効率的に絞り込めます。
比較サイトを利用することで、複数の金融機関の教育ローンを効率よく比較し、自分に合った教育ローンを見つけるのに役立ちますので、ぜひご利用ください。
11 医学部の学費調達は複数の方法を組み合わせて検討しよう

繰り返しになりますが、医学部の学費はほかの学部よりも高額なので借入可能額をよく確認して手続きを進める必要があります。
ただし、生活費などを含めて考えると、教育ローンだけではまかなえないこともあるため、医学部の学費調達は、複数の方法を組み合わせて検討することが大切です。
子どもが医学部への進学を希望している場合は、教育ローンや預貯金、奨学金などをうまく活用する必要があるといえるでしょう。
入学金など一部の費用に充てられる手段を探しているなら、教育ローンは有効な手段の1つになるので利用を検討してみてください。
Q & A
ここでは、医学部に進学する際によくある質問について、回答も合わせて紹介します。
12-1 教育ローンとは?
教育ローンとは、入学金や学費のほか、塾代など教育にかかる費用を借り入れるための目的別ローンの1つです。
資金使途が教育に関する費用に限定されているため、無担保でも比較的低金利で借りられます。
12-2 医学部にはどれくらいの費用がかかる?
進学先によって異なります。
国公立大学なら、入学から卒業までにかかる費用は約350万円ですが、私立大学の医学部に進学すると、約2,000万円~5,000万円など学校によって差があります。
12-3 教育ローンと奨学金のどちらを利用すべき?
奨学金を利用できるなら、奨学金の利用をおすすめします。借りるのは子どもで、卒業後に返済していかなければなりませんが、利息負担も少なく、返済が難しくなった際の救済措置も設けられています。
12-4 教育ローンの選び方は?
金利や返済期間、そして在学中の元金返済据置期間が用意されているかなどをチェックしましょう。
また、中には証書貸付型とカードローン型から選べるところもあります。
証書貸付型は1度しか借り入れができませんが、カードローン型は借入可能額の範囲内で都度借り入れることができます。
特徴をよく理解して、自分に合った教育ローンを選びましょう。
12-5 教育ローンの申込先はどこ?
国の教育ローンの申込先は日本政策金融公庫ですが、民間の教育ローンの申込先は提供している金融機関です。
12-6 教育ローンを利用するときの注意点とは?
金利タイプを確認することや、返済が家計に負担にならないよう、返済計画をきちんと立てることが大切です。
また、教育ローン以外の奨学金や特待生制度の利用も合わせて考えてみましょう。
- 金利ランキング
教育ローンに関するよくある質問
ここからは教育ローンについてよくある質問について、その回答と合わせて紹介します。
- 教育ローンにはどんな種類がある?
- 民間の金融機関が提供する「民間の教育ローン」と、日本政策金融公庫が提供する「国の教育ローン」の2種類あります。国の教育ローンは民間の教育ローンより金利は低く設定されている一方で利用条件を満たさないと利用ができません。民間の教育ローンは借入可能額の上限が高い金融機関もあるため、用途に合わせて申込みを検討しましょう。
- 教育ローンの金利相場はどのくらい?
- 教育ローンの金利相場は約1%~4%になります。国の教育ローンは固定金利で1.95%です(令和5年5月時点)。民間の教育ローンの金利はさまざまで、固定金利か変動金利によっても異なります。キャンペーンの適用により低金利で借りられる場合もあるので、申込みの際は事前に各金融機関のローン情報を確認しましょう。
- 教育ローンの審査基準とは?
- 教育ローンの審査基準は、契約者に返済能力があるかを重視されるのが一般的です。金融機関によって審査基準は異なりますが、他に返済をしないといけない負債があったり信用情報にキズがあると審査に通りにくい可能性があります。
- 教育ローンの返済方法は?
- 教育ローンの返済方法は、一般的に「元利均等返済」になります。元利均等返済は、毎月の返済額が均等になるように設定されるので返済計画が立てやすいのがメリットです。返済が進むほど元金が減るので利息額は減りその分元金の返済額が増えていきます。一括返済や繰上返済を利用して利息を抑えることも検討しましょう。
- 教育ローンのお金を借りるまでの流れは?
- 教育ローンを利用するには、まずローンの申込みをしてから各金融機関で実施する仮審査と本審査に通過する必要があります。本審査を受けるには契約者の本人確認書類などの書類提出が必要となります。審査に通過をして契約を締結後に契約者の口座に入金がされる流れとなります。
- 教育ローンを利用するには保証人が必要?
- 教育ローンは一般的に保証人が不要です。理由は保証会社が保証人の役割を担っているためです。保証会社とはローンの契約者が返済できなくなった際、本人に代わり借入先の金融機関に返済を行う会社です。また、国の教育ローンも教育資金融資保証基金の保証を受ける場合は保証人は不要になりますが、保証人を立てることも可能です。
- 教育ローンの借り入れまでの日数はどのくらい?
- 教育ローンの申込みから借り入までの日数は金融機関によって異なります。民間の教育ローンの場合は一般的に2週間~3週間程度です。国の教育ローンは3週間から1ヵ月と民間の教育ローンよりも時間がかかるため余裕を持って申込みをするとよいでしょう。
ライター紹介

- 氏名
- 新井 智美(あらい ともみ)
- 保有資格
- ファイナンシャルプランナー(CFP®)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
- 主なキャリア
- コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)を行う他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行うと同時に金融メディアへの執筆及び監修も行い、現在年間200本以上の執筆及び監修をこなしている。これまでの執筆及び監修実績 は1,500本以上。
関連記事
人気記事
当サイトについて
ローンプラス(以下、当サイト)は株式会社オプトにより運営・管理されています。
当サイトは各種ローン商品などに関する情報の提供を目的としており、ローンの申込み、及び契約締結の代理、媒介、斡旋などを行うものではありません。
掲載情報について
当サイトに掲載されている融資の審査に関する内容につきましては、特定の金融機関がお申込みされたお客様に対して独自に行うものであり、当社は審査の過程および結果については一切関与しておりません。また、特定の金融機関の審査への適合性、正確性、完全性について保証するものではありません。融資の審査に関する情報などに基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。ローンの申込み、及び契約締結に関するすべての決定は、ご自身の判断で行うようお願いいたします。
融資の審査に関する情報や、金利、借入条件、キャンペーンなどの詳細については、金融機関から直接提供される正確かつ最新の情報を必ずご確認ください。
なお、当サイトに掲載されている情報は無断転載、無断使用を固く禁じます。