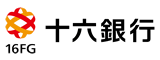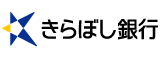【第30回】固定金利型住宅ローンを徹底解説!変動金利型との違いや借り換えのポイント

この記事は約7分30秒で読むことができます。
お急ぎの方、住宅ローンのランキングを知りたい方は、このページ下部のこちらをご覧ください。
1.固定金利型住宅ローンの特徴をタイプ別に比較
固定金利型住宅ローンは、金利が固定される期間に応じて2つのタイプに分けられます。1つが全期間固定金利型で、もう1つが固定金利期間選択型です。それぞれの特徴を以下で解説します。
1-1.全期間固定金利型
借入時に決まった金利がすべての期間に適用される住宅ローンです。住宅金融支援機構の「フラット35」は、その代表例です。民間の金融機関が独自の商品を提供している場合もあります。
メリット
- 返済期間を通して金利が変わらないため、毎月の返済額も変わらない
- 借り入れのタイミングで返済総額が確定し、返済計画や家計管理が安定する
デメリット
- 固定金利期間選択型や変動金利型と比べて金利が割高で、返済総額が膨らみやすい
- 市場金利が下がっても恩恵を受けられない
1-2.固定金利期間選択型
一定期間に限って金利が固定される住宅ローンです。固定期間の終了後に、下記の選択肢から有利なほうを選べます。
- その時点の金利で再び固定金利期間選択型を選ぶ
- 変動金利型に切り替える
金融機関によっても固定金利の期間が異なり、5年型、10年型、20年型などの種類があります。期間が短いほど金利が低いのが一般的です。
メリット
- 一定期間は金利が固定されるため、返済プランが安定する
- 固定金利期間が終了した時点で有利な金利タイプを選べる
デメリット
- 借入時に返済総額が確定しない
- 全期間固定金利型よりも返済計画が立てづらい
固定金利期間選択型には、変動金利型にある金利上昇時の125%ルールがありません。固定期間が終了した時点で市場金利が上がっていると、住宅ローンにも高い金利が適用される可能性があります。125%ルールについては後段で解説します。
2.変動金利型住宅ローンとは
変動金利型とは、借入期間中の金利が市場金利に応じて変動する金利タイプです。金融機関の定めたルールによって金利が定期的に見直されます。細かいルールは金融機関によって異なるものの、半年ごとに金利を見直し、5年ごとに月々の返済額を見直すケースが一般的です。これを、5年ルールと呼びます。5年ルールが適用されると、市場金利が変動しても5年間は金利が変わりません。
メリット
- 固定金利型よりも金利が低めに設定されている
- 市場金利が下がると毎月の返済額や返済総額が減る
デメリット
- 市場金利が上がると毎月の返済額や返済総額が増える
- 借入時に返済総額が確定しないため、返済計画が立てづらい
- 急激に金利が上昇すると、5年ルールや125%ルールの影響で未払利息が発生する
125%ルールとは
125%ルールとは、金利が急激に上昇した場合でも、返済額の見直しで125%を超える増額はしないという金融機関の業界標準です。 たとえば、毎月の返済額が10万円だったとします。金利が上がっても125%ルールがあれば、次回適用される返済額は12万5,000円以上にはなりません。
変動金利型の未払利息とは
変動金利型の未払利息は、利息の金額が毎月の返済額を超えた場合に発生します。たとえば、借り入れから3年後に金利が上がっても、5年ルールによって毎月の返済額は変わりません。 ところが、急激に金利が上がると毎月の返済額に占める利息の割合が増え、状況によっては返済額を超える場合があります。返済額を超えた利息は繰り延べられ、未払利息として扱われます。この状態になると、元本はまったく減りません。
次回の見直しで返済額を増やせば未払利息の発生を抑えられますが、125%ルールの範囲内でしか増額できない点が問題です。未払利息は後日返済しなければならない借金です。未払利息の解消が遅れると、きちんと返済していても元本が減らず、借金のみが積み上がっていく状況になりかねません。
125%ルールや5年ルールは業界標準として採用している金融機関もありますが、変動金利型の住宅ローンではルールを採用しないサービスも増えてきています。
3.固定金利型・変動金利型住宅ローンそれぞれの金利推移
金利は、返済総額に影響する重要なポイントです。全期間固定金利型では借入時に返済総額が確定しますが、変動金利型や固定金利期間選択型では、将来の金利次第で返済総額が変わる点に注意しましょう。ここでは、金利タイプ別に金利の推移を解説します。
全期間固定金利型
全期間固定金利型の代表格であるフラット35の店頭金利は、2017年以降1.11%~1.45%を推移しています。店頭金利とは、市場金利に応じて金融機関が独自に定める基準の金利です。店頭金利に各種優遇金利や審査結果が加味されて、実際に適用される金利が決まります。
固定金利期間選択型
2009年以降、固定金利期間選択型の店頭金利は、3年タイプで3.0%~3.3%付近、10年タイプで3.0%~4.0%付近を推移している状況です。
変動金利型
変動金利の店頭金利はバブル期に8%以上に達しましたが、景気減退とともに低下し、2009年以降は2.475%が続いています。
一見すると全期間固定金利型がもっとも低金利です。しかし、優遇金利が適用される変動金利型や固定金利期間選択型のほうが、実際に適用される金利は低くなります。
4.住宅ローンの借り換えは固定金利型と変動金利型どちらを選ぶ?
住宅ローンは借り換えが可能です。借り換えに際して「固定金利型と変動金利型のどちらを選ぶべきか」は、目的によって異なります。ここからは、目的別の選び方を解説します。
4-1.返済総額を抑えたい場合
返済総額を抑えたい場合は、固定金利型から変動金利型への借り換えが有効です。一方、同じ金利タイプ間の借り換えでも、金利差が大きければ返済総額が減る可能性があります。
ただし、借り換えれば必ず返済総額を抑えられるとは限りません。金利だけに注目するのではなく、融資手数料やローン保証料などのコストも含めて得になるかどうかを検討しましょう。一般的に、ローン残高1,000万円以上、返済残期間10年以上、金利差1%以上なら、借り換えで返済総額を抑えられるといわれています。
4-2.安定性を重視したい場合
返済計画や家計管理の安定性を重視したい場合は、変動金利型から固定金利型への借り換えがおすすめです。市場金利の上昇が見込まれる場合や、子どもの進学などで支出が増える予定がある場合などでは、検討する余地があります。
すでに固定期間型を利用している場合は、固定期間がより長く、かつ金利がより低い商品への借り換えが効果的です。ただし、固定期間が伸びると利息がかさんで返済総額が増える可能性があります。
家計が安定したら繰上返済を心がけ、借入期間の短縮や利息の軽減を図りましょう。繰上返済に手数料がかからないサービスを選ぶことも重要なポイントです。
5.おすすめの固定金利型住宅ローン
ここでは、固定金利型住宅ローン(新規借入)の人気商品を、固定期間別に紹介します。
5-1.10年固定金利の住宅ローン
10年固定金利住宅ローンのおすすめは、auじぶん銀行の「当初期間引下げプラン(10年固定)」です。ネット銀行ならではの低金利やネットで手続きが完了するWeb完結が特徴で、スピーディーに融資を受けたい人にも向いています。
充実した団体信用生命保険(団信)も魅力のひとつです。団信とは、加入者が死亡・所定の高度障害状態になった際に返済が免除される仕組みです。auじぶん銀行の団信では、一般団信とがん50%保障団信が金利上乗せなしで利用できます。
auじぶん銀行「当初期間引下げプラン(10年固定)」
- 適用金利:年0.525%(2021年4月時点)
- 申込条件:申込時の年齢が満20歳以上満65歳未満、前年度の年収が200万円以上、など
- 借入金額:500万円以上2億円以下
- 借入期間:1年以上35年以下(借り入れから10年固定金利)
- 団信加入:必須
- 団信の種類:一般団信、ワイド団信、がん50%保障団信、がん100%保障団信、11疾病保障団信
- 一部繰上返済手数料:無料
- 融資事務手数料:借入金額の2.20%(税込)
5-2.20年固定金利の住宅ローン
20年固定金利住宅ローンのおすすめは、ソニー銀行の「固定セレクト住宅ローン(20年固定)」です。返済口座への資金移動が無料、仮審査が最短60分、Web完結対応など、使いやすいサービスが多数用意されています。借りた後の手数料を抑えやすい点がソニー銀行の特徴で、5年ルールと125%ルールは採用していません。
ソニー銀行「固定セレクト住宅ローン(20年固定)
- 適用金利:年1.180%(自己資金10%以上の場合、2021年5月時点)
- 申込条件:申込時の年齢が満20歳以上満65歳未満、前年度の年収が400万円以上、など
- 借入金額:500万円以上2億円以下
- 借入期間:1年以上35年以下(借り入れから20年固定金利)
- 団信加入:必須
- 団信の種類:一般団信、ワイド団信、がん団信50、がん団信100、3大疾病団信、生活保障団信
- 繰上返済手数料:無料
- 融資事務手数料:借入金額の2.20%(税込)
5-3.35年固定金利の住宅ローン
35年固定金利住宅ローンの代表格はフラット35です。なかでも、取り扱い実績ナンバーワンのARUHIが提供する「ARUHIフラット35」が人気です。フラット35の申込条件には年収の制限がありませんが、住宅が技術基準を満たさない場合は利用できません。
幅広く病気やケガに備えたい場合は、「ARUHI全疾病保障(入院一時金付)」と団信の併用も可能です。特約料の支払い方法は2通りで、年一括払いと金利上乗せ方式から選べます。
ARUHI「ARUHIフラット35」
- 適用金利:借入期間15年~20年で年1.24%、21年~35年で1.37%(自己資金10%以上で住宅金融支援機構の団信加入の場合、2021年4月時点)
- 申込条件:申込時の年齢が満70歳未満、住宅が技術基準に適合する、など
- 借入金額:100万円以上8,000万円以下
- 借入期間:1年以上35年以下
- 最短借入期間:原則として15年
- 最長借入期間:「35年」と「80歳-申込時の年齢」のうち、短いほう
- 団信加入:任意
- 団信の種類:住宅金融支援機構の新機構団信、夫婦連生団信、新3大疾病付機構団信
- 繰上返済手数料:無料
- 融資事務手数料:直接問い合わせ
※2021年5月13日時点の情報を記載しています。
特徴や金利を正しく理解して目的に合う住宅ローンを見つけよう
固定金利型の住宅ローンは、借入期間を通じて返済額が変わりません。特に安定した返済計画を重視する人に向いています。一方、市場金利の状況によっては、変動金利型のほうが返済総額を抑えやすい場合があります。
金利タイプの特徴や商品の内容を正しく理解して、自分のライフステージや借り入れの目的に合った最適な住宅ローンを選びましょう。
- 金利ランキング
ライター紹介
- 氏名:
- ひまり
- 主なキャリア:
- Webライター歴4年。元SE、専攻は心理学。ITおよびカードローンやキャッシング、税金関係の記事が得意分野。複数メディアのライターとして寄稿している。
- 保有資格:
- 基本情報技術者試験
住宅ローンに関するよくある質問
ここからは住宅ローンについてよくある質問について、その回答と合わせて紹介します。
- 変動金利と固定金利どちらがよい?
- 変動金利は固定金利より金利が低い傾向にありますが、金利動向に連動して変動するため、貯蓄に余裕があったり、今後収入が増える見込みがある人に向いていると言えます。一方、固定金利は一定期間同じ金利のため完済までのスケジュールを立てやすい点がメリットになり、無理なく返済したい人に向いていると言えます。
- 住宅ローンの審査基準とは?
- 住宅ローンの審査基準は返済能力をチェックするために「借入時・完済時の年齢」「健康状態」「勤務先・勤続年数」「年収」「担保評価」などになります。 物件の担保価値は契約者が返済できなくなった場合を考慮して評価されるため、借入前に不動産の価値を調べておくとよいでしょう。
- 住宅ローンの返済方法は?
- 住宅ローンの返済方法には「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があります。元利均等返済とは返済額が毎月一定のため、返済プランを立てやすいことが特徴です。元金均等返済は返済が進むと返済額が減っていくため、元利均等返済と同期間での返済では返済総額が少なくなります。
- 住宅ローンでお金を借りるまでの流れは?
- 住宅ローンを借り入れるまでの流れは、ローンの申込みをしたあと仮審査、住宅の売買契約、本審査を経て契約、融資実行(住宅の引き渡し)となります。本審査では本人確認資料や物件確認資料、収入に関する書類などが必要となり、本人属性や他社借入状況など総合的に判断した上で借入可能額の上限が決定します。
- 住宅ローンを利用するには保証人が必要?
- 住宅ローンは基本的に保証人なしでお金を借りることができます。理由としては購入する自宅が担保となるため、契約者が返済ができなくなった時は住宅を売却することで資金を回収できることや、保証会社に一定の保証料を支払うため、保証会社が保証人の代わりの役割を担うことができるためです。
- 住宅ローンの借り入れまでの日数はどのくらい?
- 住宅ローンの借り入れまでの日数としては事前審査が1週間程度、本審査が2週間~3週間程度かかるため、およそ1ヵ月ほどかかります。必要書類に不備があったり、借入希望金額が大きい場合には審査が長期化し、更に時間を要します。
ライター紹介
- 氏名
- ひまり(ひまり)
- 主なキャリア
- Webライター歴4年。 もともとシステムエンジニアだったが、結婚、出産、育児と専業主婦の期間を活かして知識を習得し始めたことがきっかけで、現在はカードローンやキャッシング、税金関係の記事を得意とし、複数メディアのライターとして寄稿している。現在は簿記の勉強中。
関連記事
人気記事
当サイトについて
ローンプラス(以下、当サイト)は株式会社オプトにより運営・管理されています。
当サイトは各種ローン商品などに関する情報の提供を目的としており、ローンの申込み、及び契約締結の代理、媒介、斡旋などを行うものではありません。
掲載情報について
当サイトに掲載されている融資の審査に関する内容につきましては、特定の金融機関がお申込みされたお客様に対して独自に行うものであり、当社は審査の過程および結果については一切関与しておりません。また、特定の金融機関の審査への適合性、正確性、完全性について保証するものではありません。融資の審査に関する情報などに基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。ローンの申込み、及び契約締結に関するすべての決定は、ご自身の判断で行うようお願いいたします。
融資の審査に関する情報や、金利、借入条件、キャンペーンなどの詳細については、金融機関から直接提供される正確かつ最新の情報を必ずご確認ください。
なお、当サイトに掲載されている情報は無断転載、無断使用を固く禁じます。